人格の5因子モデル(ビッグファイブ)に基づいて開発されたNEO-PI-Rという心理検査があります。これは、人格を細かい特徴まで捉え、尚且つ、包括的に理解するために、5つの次元を細かく細分化させています。
今回は、5因子(「N 神経症傾向」「E 外向性」「O 開放性」「A 協調性」「C 誠実性」)のうち、「N 神経症傾向」についてまとめてみたいと思いますので、自己理解を深めるにあたり、参考にしてみてください。
神経症傾向の包括的理解
神経症傾向とは、情緒的な不安定さや、ネガティブで否定的な感情を経験しやすい傾向かどうかを示しています。トラブルやプレッシャーのかかる仕事で、ネガティブな出来事に対してどう反応するかなどでは、その違いがよく現れます。
つまりこの値が高いと、ストレスに敏感で、不安、怒り、悲しみ、困惑といった感情を経験しやすくなります。なかでも些細なことでカッとしやすい人は、この値が高いと、怒りをコントロールするのが難しくなり、誤った対処をしがちです。反対に、この値が低いと、精神的な安定感は高く普段からリラックスしており、何か問題が起こった時でも慌てず、落ち着いて対処できる、というのが一般的な理解です。
NEO-PI-R人格検査では、さらに細かく6つの下位次元に分けられるので、ご自分の特徴をより深くつかみやすくなります。では、下位次元をみていきましょう。
神経症傾向の6つの下位次元
下位次元1 不安
ここでは、漠然とした不安を感じやすい場合も、また、何か特定なことへの恐れを抱きやすい場合も、両方を含んでいます。この値が高いと、緊張しやすく、不安を感じやすいので、人に対して気遣うだけでなく、時に人を恐れたり、物事に対して悩みがちになるなど、神経過敏なところがみられます。反対にこの値が低いと、普段から落ち着いていて、リラックスしている印象があります。たとえ失敗しそうなことに対しても、あまり深く悩まない傾向が顕著に見られます。
下位次元2 敵意/攻撃性
どれくらい怒りを経験しやすいかを示しています。ここには、嫌悪感やイライラ感といった情緒的なものも含まれます。この値が高いと、気が短くて、すぐにカッとしやすい傾向がみられます。決して攻撃性そのものを測定しているわけではありませんが、些細なことにも過敏に反応し、イラッとするので、結果的に攻撃的になることが多くなるという印象があります。反対に低ければ、おおらかで寛容性があり、激しい怒りの感情に囚われるということがありません。
下位次元3 抑うつ
誰もがネガティブな感情を経験しますが、ここでは、健康的な人がどれくらいうつ的な情動を経験しやすいかを示しています。高い値であれば、悲しみや絶望感、孤独や罪悪感に浸りやすく、容易に心が折れてしまったり、くじけてしまいがちです。反対に低値であれば、うつ的な感情に襲われても、それは一瞬のことであって、長引きません。元気でくったくない、というわけではありませんが、人生においてこのような感情を経験しにくいのです。
下位次元4 自意識
ここでいう自意識とは、自分の存在や行動・考え方を意識することを指し、人からどうみられているかを気にしたり、恥ずかしさや当惑(どうしていいか戸惑ってしまうという)を経験をしやすいかを示しています。高い値であれば、まわりに人がいると居心地の悪さを感じます。冷やかしに対しても敏感に反応し、劣等感を抱きやすくなります。またそれが度重なれば、社会不安へとつながりやすくなります。反対に低い値であれば、どんな状況に置かれても、他人の言動はさほど気にならず、何か言われたとしても、聞き流すことができ、取り乱すことは少ないです。
下位次元5 衝動性
一般的な衝動性とは、深く考えたり、計画なしに突発的な行動をとってしまうことを指しますが、ここでは、湧き起こる欲求への切望(どうしても欲しい!など)や、怒り(絶対に許さない!など)をコントロールできるかどうかを示します。高い値だと、あとで後悔することがわかっていても、その場では、タバコやお酒、食べ物や欲しいものを我慢したり、また、湧き起こる怒りを抑えることが難しくなります。低い値だと、誘惑を跳ね除けることを難しいことだとは感じません。例えフラストレーションを感じたとしても、許容範囲が大きいのです。
下位次元6 傷つきやすさ
他人の言動や出来事に対して敏感に反応し、容易に心が傷ついてしまう傾向があるかを示しています。高い値だと、緊急事態に直面すると、パニックになりやすいです。ストレス対処に自信が持てないため、希望を抱きにくく、また、自分でなんとかしようと思う反面、誰かに頼りたくなるといった依存的な面が見られます。低い値だと、困難な事態に遭遇しても、漠然と自分で対処できると感じますし、実際に統制していくことができます。
これらの下位次元をまとめて総括的にみた場合、一般的に神経症傾向の高い人・低い人は、どのような特徴を示すのか「感情面」「行動面」「対人関係」「職務適性に分けてみてみましょう。
神経症傾向の高い人・低い人の特徴
神経症傾向の高い人
<感情面>
ちょっとした刺激にも敏感で、ストレスや不安を感じやすい。
気分の変動が激しい。
<行動面>
衝動的に行動しやすく、自分をコントロールすることへの難しさがある。
<対人関係>
人からの評価が気になってしまう。
<職務適性>
細かいところに注意を払う必要のある業務や、高いリスク管理が求められる職種に向いている可能性がある。
神経症傾向の低い人の特徴
<感情面>
情緒が安定していて、ストレスフルな状態に置かれても耐性が高い。
<行動面>
冷静で落ち着いている。
<対人関係>
人からの評価に左右されにくい。
<職務適性>
リーダーシップを必要とする職種や、ストレスの高い環境での職種に向いている可能性がある。
いかがだったでしょう。
この傾向の高い・低いは、決してマイナスではありません。むしろ、自己理解を深めて上手にバランスを取れれば力として生かせると感じています。例えば、高い値であったとしても、用心深さはリスクを減らすことに貢献するでしょうし、守備範囲をしっかり固めることで失敗を最小限にできます。その結果、信頼につながることもできるからです。大切なのは、行き過ぎてしまわないこと。そのための対策を考えていけたらと思います。
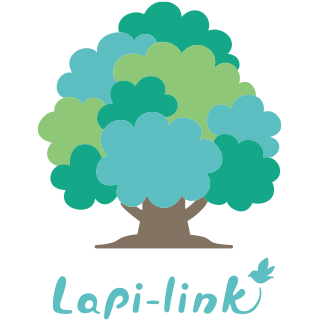

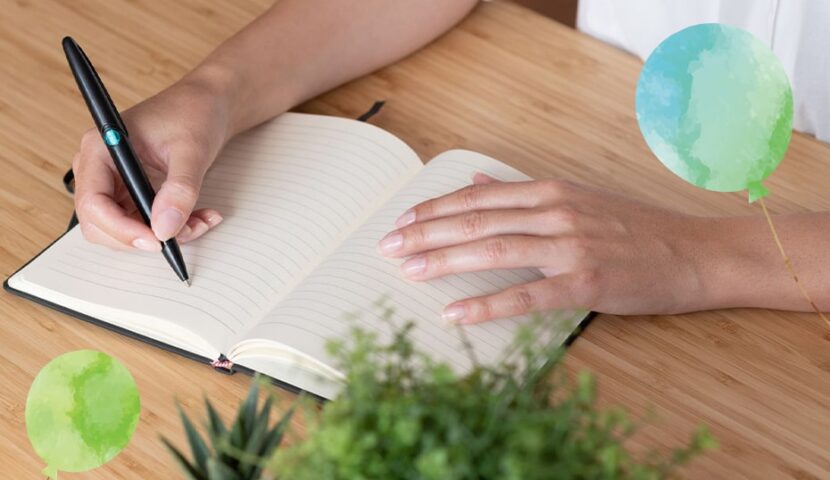










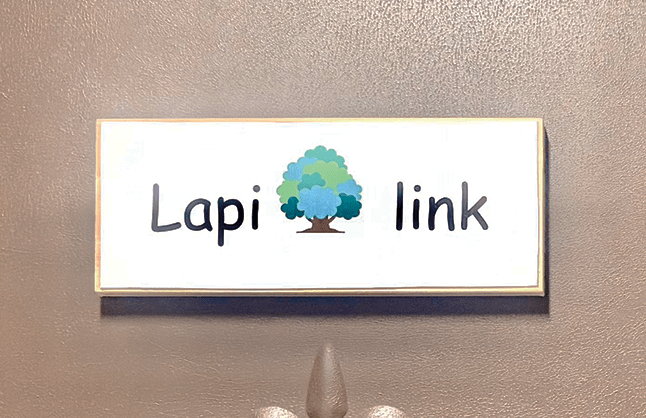
コメント