人がどのようにして結婚相手や長期的なパートナーを選ぶのかについて研究する分野があります。それが「配偶者選択」です。遺伝子を次世代に残し、生き延びるための免疫力強化を考え、生殖を成功させることを目的にしていると主張する進化心理学や、好意を抱いてくれる人を好きになる互恵性や、似たもの同士の類似性、物理的に近い存在に好意を抱きやすくなる近接性を主張する社会心理学など、いろんな視点があります。そこで、今回はフロイトやのちの精神分析家たちが提唱した精神分析的観点からみた配偶者選択についてまとめてみたいと思います。
親に似た相手を選択するという仮説
フロイトといえば、幼少期の男の子が経験する「エディプス・コンプレックス」があります。これはちょうど4歳ごろの男の子が母親に愛情を抱き、父親を競争相手と見なす心理のことで、後に、母親に似た特性を持つ相手を無意識に選びやすいという<親和性仮説>になります。この時「では女の子は?」という疑問が湧いてきますでしょうが、同じことです。この場合は「エレクトラ・コンプレックス」といって、女の子が抱く父親への愛着があり、配偶者選択においても、無意識に父親に似た相手を選択しやすいといわれる説です。
一体感を求めて選択するという仮説
子どもが誕生する時の、母親の胎内から出てくるという分離体験が、無意識に反動で「一体感」を求めるように心が働くという説があります(オットー・ランク「出生トラウマ」)。男女問わず、配偶者選択においても「自分を受け入れてくれる存在」を求める、「自分に安心感を与えてくれる相手」を求めることにつながるとされる説です。
母親との関係が影響するという仮説
乳児期の母親との関係が、のちの恋愛や結婚に影響を与えるという「対象関係論」を提唱したメラニー・クラインの説です。つまり、幼少期に母親との関係が安定していた人は、健康的で安定した関係を築きやすいけれど、反対に、不安定な愛着のカタチをもっていた人は、男女関係なく、支配的な相手を選択したり、依存的な相手を選ぶ傾向があるという説です。
無意識に自分の欠けた要素を持つ相手を選ぶという仮説
フロイトの愛弟子であり、のちにフロイトと決別し、独自の理論を発展させていったユングは、人間の無意識の中には、男性の中にある女性的な側面の「アニマ」と、女性の中にある男性的な側面の「アニムス」があるといいました。そして、人は無意識に、自分の中に欠けている要素(アニマ/アニムス)を持つ相手に惹かれると説いたのです。例えば、論理的な思考を苦手とする感情的な女性が、常に冷静でロジカルな男性に惹かれたり、逆も然りで、理屈っぽくて感情を抑える男性が、感受性が豊かで直感的な女性に惹かれるというのがいい例です。
成熟した愛・未熟な愛という仮説
親との関係にわだかまりがあったり、未解決な問題を抱えてる場合、相手を理想化させ、自分を満たしてくれる存在として求めていくうちに、「依存的/支配的」な関係になりやすいという説です。親との関係が安定したものであれば、相手を独立した存在として愛することができるといわれています。
いかがだったでしょう。
精神分析の視点からみた配偶者選択は、偶然のように見えて、実は偶然ではなく、無意識の心の動きが関係しているというわけです。「親との関係」「幼少期の体験」「無意識の親への欲求」などが絡み合い、親に似た相手を選んだり、無意識の欲求を満たそうとして相手を求めたり、自分にないものを持っている相手に惹かれたりしながら、恋愛や結婚相手を選んでいると考えるのです。つまり、よくいう「赤い糸で結ばれた関係」というのは、お互いに無意識に求め合っているものがあって、その結果、お互いに引き合ったという、必然の関係なのかもしれませんね。
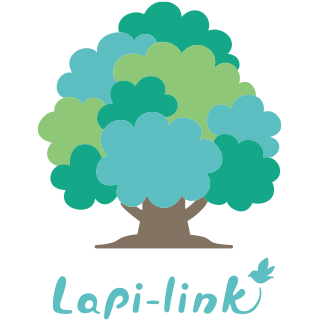


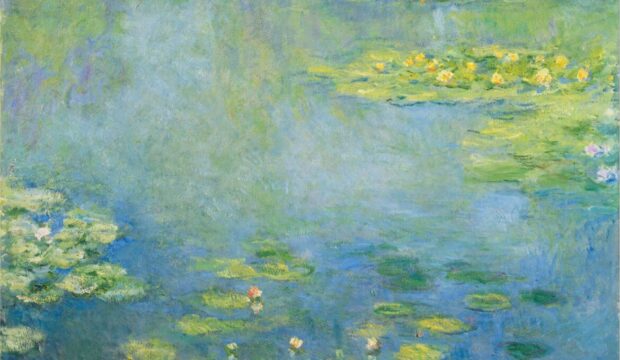







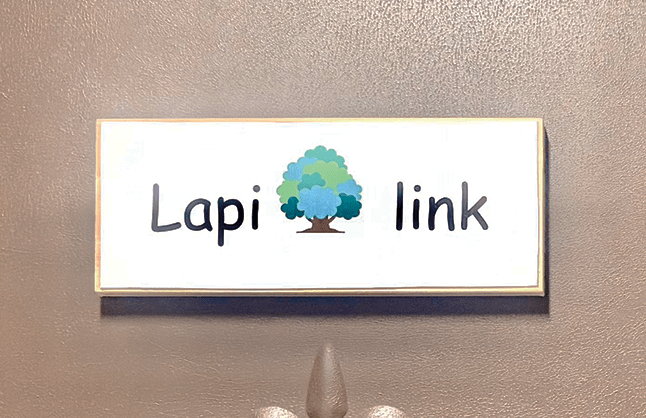
コメント