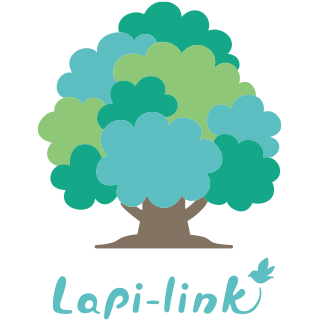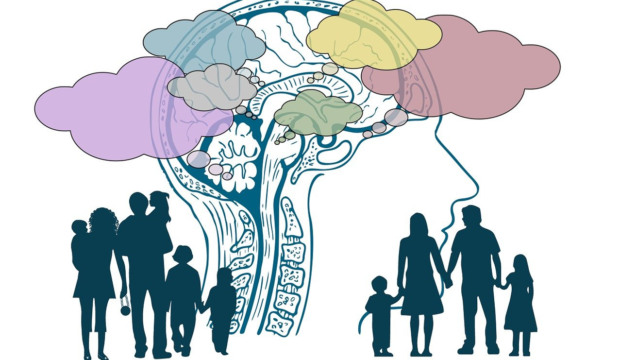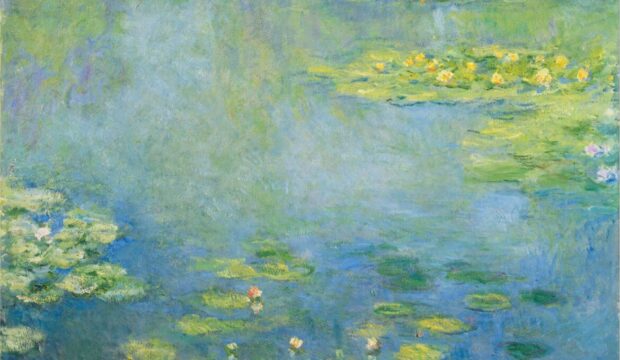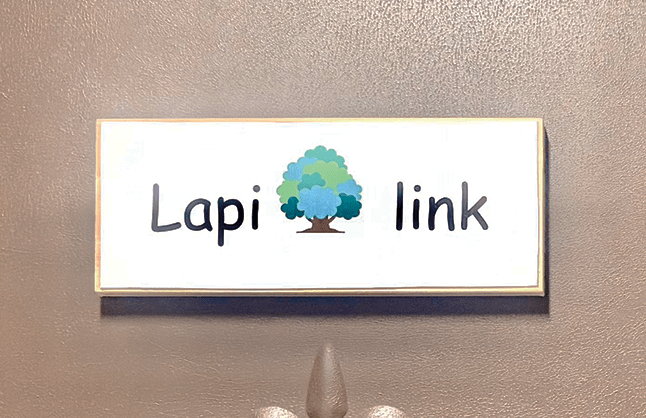スキーマ療法は、心理療法の中でも新しいアプローチとして注目されるようになってきました。そこで、初めて聞くという方にもわかりやすくお伝えできたらと思います。
スキーマ療法とは
スキーマ療法は、認知行動療法(CBT)を提唱した米国の心理学者ジェフリー・ヤングが、1990年代に新たに開発した治療法で、認知行動療法(CBT)をさらに深めた心理療法になります。認知行動療法とは、認知のしかた(つまり、ものの考え方・受け取り方など)を柔らかくすることで、感情に働きかけ、気持ちを軽くさせて、ストレスを減らしていこうというものです。認知行動療法には様々な技法がありますが、総じてストレス改善に働きかけていきます。スキーマ療法では、それをさらに深めるため「そもそも生きづらさをもたらす認知はどうやって形成されたのか」という点に焦点を当てていきます。つまり、幼少期の体験にまで遡り、どんな経験を通して、どんな考え方を形成していったのか、というところまで深めていくのです。ですから認知行動療法だけではなく、愛着理論や精神分析を統合させて取り組んでいく必要がありますし、パーソナリティの特性や、抱えている問題とのつながりを紐解いていくという、認知行動療法よりも少し大掛かりなものになりますので、専門家にとっても深い知見と経験値が必要になってきます。
スキーマ療法を理解するために、いくつか知っておいていただきたい言葉がありますので、合わせて解説していきますね。
スキーマとは
まず、「スキーマ」についてです。スキーマとはちょっとわかりにくいものなので、別の角度から解説してみますね。
例えば、プログラミングの世界では、スキーマはデータベースの構造に用いられているそうです。個々の細かいデータをどうやって管理するかという約束事のようなものを指すといわれていますが、これを心理学に置き換えてみるとわかりやすいです。心理学では、私たちが知らずに築いてきた「考え方」「行動」を取りまとめている潜在意識のようなものを指し、「信念」や「確信」といった、「信じて疑わない」「信じ込んでいる」という内面的な枠組みのことをいいます。これらは感情と密接なつながりがあり、容易に感情を揺さぶりますが、それがいつも割と同じようなパターンになっているのが特徴です。(例:嫌われている・否定された・怒られるなど特有の考えがよぎり、不安や恐怖が湧いてきて、激昂したり逃げ出そうとする行動の流れをつくるなど。)
つまり、心理学でいうスキーマとは、幼い頃に形成された「自分をどうみるか」「他人をどうとらえるか」「社会をどうとらえるか」といった内面的枠組みで、深い信念や、それに伴う感情パターンを指します。人によっては、その場にそぐわない「不適応なスキーマ」を持つことで、かえって苦痛を感じやすくなったり、強い回避傾向をもったり、怒りに囚われたり、困った行動を引き起こしやすくなるのです。
不適応スキーマ
不適応スキーマは、幼い頃の養育者との関わりや、経験に基づいて作られています。子どもは「愛されたい」「理解されたい」と思うのは当然です。ところが、この当然の欲求がきちんと満たされなかったら…と仮定してみます。そうなると、どんなにつらい環境下であっても、なんとか生き延びていかなければならないわけです。苦しい状況の中でも、必死に生き延びようとするために身につけてきたものが「不適応スキーマ」なのです。
スキーマ療法では、まずこの「不適応スキーマ」を特定させていきます。そして、丁寧に掘り下げていく中で、新しいスキーマを形成し、もっと健康的な対処ができるように、対処法を身につけていきます。そうすることで、後の人生がもっと満たされたものとなるようにサポートしていくのです。
では、具体的にどんな不適応スキーマがあるのかをみていきましょう。
それを理解するにあたって、そもそも子どもが抱く当然の欲求とは何か、について説明します。養育者に対して子どもが抱く欲求を「中核的感情欲求」と呼び、大きく5つに分類したものが以下になります。
感情欲求①「愛されたい」
感情欲求②「有能な人になりたい」
感情欲求③「自律した人になりたい」
感情欲求④「自由にのびやかに生きたい」
感情欲求⑤「感情や思いを自由に表現したい」
これら「中核的感情欲求」が満たされなかったことで、「不適応スキーマ」が形成されると考えた心理学者ジェフリー・ヤングは、不適応スキーマを以下の5領域18種類に分けて提唱しました。順を追って解説していきますね。
第一領域「人との関係を断絶・拒絶させてしまう」スキーマ
(感情欲求①「愛されたい」が満たされずに生じる不適応スキーマ)
(1)見捨てられ・不安定スキーマ:人は自分をきっと見捨てるに違いない
(2)不信感・虐待スキーマ:人はきっと自分を攻撃してくるに違いない
(3)誰からも愛されないスキーマ:人は自分を愛してはくれない
(4)欠陥がある・恥スキーマ:自分は人として欠陥のある存在だ
(5)孤立・孤独スキーマ:自分はいつも一人ぼっちだ
第二領域「自信がない・一人じゃ怖くて何もできない」スキーマ
(感情欲求②「有能な人になりたい」が満たされずに生じる不適応スキーマ)
(6)無能・依存スキーマ:自分は無能だから一人じゃできない
(7)被害を受けやすいスキーマ:自分は弱いから強いものや病気にもすぐにやられてしまう
(8)すぐに同調する巻き込まれスキーマ:いつもまわりに同調していないと安心できない
(9)失敗スキーマ:何をやってもうまくいかない・失敗するに違いない
第三領域「ルールや規範の欠如」スキーマ
(感情欲求③「自律した人になりたい」が満たされずに生じる不適応スキーマ)
(10)尊大スキーマ:自分は特別扱いされるべきで、権利を要求するのは当然だ
(11)自制欠如スキーマ:ガマンなんかしなくて好き勝手やるべきだ
第四領域「過剰な抑制・警戒」スキーマ
(感情欲求④「自由にのびやかに生きたい」が満たされずに生じる不適応スキーマ)
(12)否定・悲観スキーマ:どうせ失敗するしいいことなんて起きない
(13)感情抑制スキーマ:感情は表に出さない方がいい
(14)厳密な完璧主義スキーマ:全てにおいてきちんとすべきだ
(15)罰するスキーマ:失敗したら罰を受けるべきだ
第五領域「他人軸・他者優先」スキーマ
(感情欲求⑤「感情や思いを自由に表現したい」が満たされずに生じる不適応スキーマ)
(16)絶対服従スキーマ:嫌われたくないから服従する
(17)自己犠牲スキーマ:犠牲を払ってでも相手の意向を優先すべき
(18)評価・承認希求スキーマ:よく思われたい・まわりの評価が過剰に気になる
不適応スキーマへの3つの対処法
人はこれら不適応スキーマが活性化すると、なんとか対処しなければと瞬時に動きます。この場合、よくみられる対処の方法に3つのスタイルがあります。それが「服従」「回避」「過剰補償」です。
「服従」とは
ひたすらスキーマに従う(言いなりになる)ことで、それ以上の被害を防ごうとします。
(例:「自分は一人で生きていけないし、何もできない弱い存在だ」→依存的に行動する)
「回避」とは
スキーマにかかわる思考や感情などの体験を避け続け、スキーマが存在しないかのように振る舞い、活性化されそうになったら、素早くその状況から離れたり、自らの反応を抑え込もうとします。
(例:「自分は人から愛されない」→集まりは苦手、人と関わりたくない)
「過剰補償」とは
スキーマと正反対のことが本当の事実であるかのように振る舞い、スキーマと闘おうとします。または、スキーマを避けてまったく違う存在であろうと行動します。
(例:「自分の感情をコントロールできない」→自分はいつも正しい、周りはバカばっかりだ)
不適応スキーマは、ある場面において瞬間的に湧き起こります。そして、どう対処するかという「対処パターン」と合わせ、一時的な「運用パック」として保管されます。そうすることで瞬時に「運用パック」に移行できるようにしておくのです。このように、経験する瞬間的な心の状態を「スキーマモード」と呼びます。
スキーマモード
そもそも「モード」とは、<今、ここ>の状態や反応のことを指します。私たちの心の状態は常に変化し続けていますよね。その一瞬一瞬、その時々の「心の状態や反応」のことを「モード」と呼びます。そして、ここに、先ほど説明した心の奥深くに刻まれた「スキーマ(信念)」が影響を与えると考えてみるのです。不適応スキーマはいつも活性化しているわけではありません。静かにおとなしくしている時がたくさんあります。ただ、ある状況に置かれた時に、突然、活動を始め、暴走してしまうのです。人には本来たくさんのモードがありますが、ヤングらは、一般的なスキーマモードを4つのカテゴリーにグループ化させ、全部で10モードを特定していますので、簡単にご紹介していきますね。
【1】非機能的な子どもモード
①傷ついた子どもモード
「自分には欠陥がある・愛されない・孤独・捨てられる」といった信念によって「自分は望まれていない・価値がない・どうしようもない存在だ」という考えを持ちやすくなり、「悲観的・抑うつ的」な状態に陥りやすくなります。また、そのような自分を他人に知られないように隠そうとすることもあるため、利己的に振る舞ったり、注目を集めたがったり、よそよそしく振る舞ったり、本当の性質とは異なる行動をとって別人格のように振る舞うこともあります。本当は人を求めていて、仲間や愛情を望んでいるにもかかわらず、人から拒絶される恐怖から身を守るための行動をとってしまうのです。
②怒っている子どもモード
「見捨てられた・虐待された・愛情をかけてもらえなかった」ことに対して怒っていて、中核的感情欲求が満たされないと感じた時や、不公平な扱いを受けたと感じた時に、強い怒りを表現します。根底には強い被害者意識や苦々しい感情を抱えており、否定された・嫉妬・怒り・悲観的思考につながりやすくなります。この状況下では、激しい行動化や衝動(叫ぶ・物を投げたり壊す・自分を傷つける・他人に危害を与えるなど)に駆られます。そして、激怒する背後には、強い不安を感じてイライラしたり、傷つきやすい状態になっているのです。
③衝動的な子どもモード
自己制御することのない、欲望や感情のおもむくままに行動する子どもの状態にです。ルールや規範などない、何でもありのモードで、それはまるで、しつけられる前の幼児のようなモードです。具体的な行動では、無謀な運転、薬物乱用、ギャンブル、自殺念慮であったり、衝動的に壁を殴ったり、責任を無実の人に押し付けて激怒する、といった場合もあります。また、不特定な人との性行為だったり、とっさに逃げようとする軽率さだったり、幼児的なカンシャク を見せることもあります。
【2】非機能的な対処モード
④従順降伏モード
他人の言いなりになって、依存的な対処スタイルになります。それはまるで、無力な子どものように人に服従します。そして、置かれる状況に対して「抵抗できない」「無力感」「悲しみ」「罪悪感」「怒り」といった感情につながりやすくなります。このモードに入っている人は、自分のスキーマに対してとやかく考えることは意味がないので、抵抗せずに受け入れるべきだと強く信じています。対人関係でも、受動的で、依存的になることが多く、生活の中で人を喜ばせて、対立を最小限に抑えることで、さらなる危害を避けるように努めていきます。
⑤防衛遮断モード
感情的に引きこもって人との接触を遮断したり、孤立したり、回避行動をとるなどの対処スタイルになります。「内にこもる」「何らかの自己刺激を求める(薬物やお酒といった嗜癖行動)」など、さまざまな回避的な手段を用いて心理的苦痛を防ごうとします。現状に対して対処するスキルが不十分なのに、現実には対処を求められるため、そのような場面において恐怖を感じ、ストレスから身を守ろうとして無感覚になることで対処しようとします。
⑥過剰補償モード
極端な厳格さで、自分の中にあるスキーマ(信念)に徹底的に対抗しようとします。具体的には、攻撃的になったり、反抗心を強めたり、人をコントロールしようとしたりします。例えば、相手を「信用できない」「自分を傷つけるに違いない」と思えば、される前に先手を打って、自分から傷つけようとしますし、懲罰的なモードを持つ相手に対しては、極端な態度になって許しを乞おうとし、結果的に相手をコントロールしようとします。
【3】非機能的な親モード(内在化された親モード)
⑦懲罰的親モード
自分には欠陥があって、ちょっとした間違いも厳しく罰せられて当然だ、と思っています。自分のような人間は、生きているだけで罰せられるのは当然だと極端に思う場合もあります。とにかく自分に厳しく、多くの人が基準を満たさない平均的な状況下であっても、自分だけは許すことができません。
⑧要求的親モード
過度に高い基準を押し付けて、絶対に達成させなければと自分に強いプレッシャーをかけます。
このモードを経験すると、どれだけうまくやっても、どれだけ努力しても、自分のパフォーマンスは不十分だと感じます。そして、休息、楽しみ、リラックスする行為は受け入れられず、たくさんのことを達成させるために、注意を集中し続けなければならないと考えます。ただ、要求の厳しい親モードでは、自分の成果に対してプレッシャーや不満を感じるのですが、必ずしも、罪悪感、恥、無価値感を感じているわけではありません。
【4】健康的な(大人/子ども)モード
⑨健康的な大人モード
健康的な大人の状態を表します。健康的な大人は、自分自身を常に客観的にモニターしながら、そのあり様を理解し、受け入れていきます。そして、必要であれば、何らか対処することができます。自分の中核的感情欲求をよく理解しており、自分で自分の欲求を適切な形で満たそうとします。その結果、以下のような行動がみられるようになります。
◉意思決定することに抵抗を感じません
◉問題を解決する力があります
◉行動する前に考えることができます
◉適度に野心的です
◉自分で限度や制限を設定することができます
◉自分や他人を育成できます
◉人と健全な関係を形成できます
◉全ての責任を負うことができます
◉物事を最後までやり遂げます
◉物事に楽しんで参加します
◉他人との間に境界線を設けることができます
◉大人として楽しい活動や興味を持ちます
◉健康に気を配ることができます
◉自分を大切にすることができます(wiki-pedia参照)
つまり、健康な大人モードでは、常に希望を絶やさず、努力することができるのです。過去に囚われるのではなく、過去を許し、自分のことを「困難を生き延びたサバイバー」と見なしますが、決して被害者だとは思いません。そして、健康的に自分の感情を表現するようになります。
⑩しあわせな子どもモード
中核的感情欲求が満たされていて「愛されている」「一人ではない」と感じられ、安心感に包まれ、楽しみや喜びに満ちた子どもの状態を示します。遊び心があり、世界に対してもワクワクした楽しさや驚きを感じます。不適応スキーマの活性化がないため、健康的な時間を過ごすことができます。また健康な大人は、同時に、この「しあわせな子どもモード」を養うことで、バランスの良さを発揮していきます。
スキーマ療法のすすめ方
いかがだったでしょう。スキーマ療法をすすめていくにあたり、様々な言葉があることがおわかりいただけたでしょうか。ここでご紹介したものはほんの一例ですが、とても重要なワードになります。
では、これらの知識を踏まえた上で、どのようにすすめていくのか、簡単に概要をお伝えしますね。
<Step1>自分をつかむ
自分の「今」をつかんでいきます。特に、何かうまくいかないことに遭遇した時がチャンスであり、自分に気づくよいきっかけになります。この時は、ぐるぐると悪循環の思考に入り込んでいる状態から自分を救出し、ちょっと離れて自分を眺めてみるのです。ここが最初の関門です。多くの場合、長きにわたって同じ思考をくり返してきていますので、気づいたとしても、すぐに元のぐるぐる悪循環思考に戻ってしまうからです。時には、専門家の力を借りながら、認知行動療法の技法をフル活用して、自分を眺める技術を習得していくことも重要です。
「自分をつかむ」ということの中には、ご紹介した知識に沿って、満たされなかった「中核的感情欲求」や「不適応スキーマ」、そしてどんな対処をする傾向があるかを観察しながら、「スキーマモード」を捉えていきます。そして心の中に居座っている「傷ついた子ども」や「傷つけようとする大人」の存在をつかんでいきます。
<Step2>健康な大人モードを育てる
自分の中にある「傷ついた子ども」や「傷つけようとする大人」の存在に気づけたら、今度は「健康的な大人」を大きく育てていきます。「健康的な大人」とは、どんな時にも必ず味方になってくれる存在で、常によき理解者であり、心からしあわせになることを願ってくれています。正しい道へといざなってくれる、優しくて、強くて、頼りがいのある大きな存在です。何事もない穏やかな時には、自分の中に「健康的な大人」が育っています。ですから、どんな人の中にも「健康な大人」はいるのです。その存在を意識しながら、さらに大きく育てていきます。
具体的なやり方としては、「傷ついた子ども」と「傷つける大人」の間に割って入り、「どうした?」「何があった?」「大丈夫?」と傷ついた子どもに優しく声をかけ、傷つける大人に対して毅然と立ち向かっていきます。「何をする!」「あっちにいけ!」「二度と近寄るな!」と怯まず追い払うのです。そして、怯えていた「傷ついた子ども」を優しく抱きしめてあげるのです。
<Step3>不適応スキーマを否定し反証していく
「不適応スキーマ」が徐々に弱まってきたところで、今度はそれまでの「不適応スキーマ」を否定し、反証させていきます。具体的なやり方としては、「本当にそうだろうか?」「必ずしもそうとは限らない」「なぜかというと…だからだ」というように、冷静に、かつ論理的に裏付けながら、一つ一つ丁寧にくり返し反証させていきます。
<Step4>新しいスキーマを育てる
「不適応スキーマ」に代わり、自分を健康的でしあわせにいざなっていく「新しいスキーマ」を育てていきます。
これまで長きにわたって使い続けてきた「不適応スキーマ」ですが、小さな感情の動きも敏感に捉えながら、何度もくり返し取り組んでいく中で徐々に小さくしぼみ、新たに「新しいスキーマ」が刻まれていきます。
いかがだったでしょう。大枠をなんとなくつかめていただけたら幸いです。自分をとらえることは誰でも難しく、意識しなければなかなか気づきにくいものです。でも反対に、気づければ変えることができる、ということでもあります。そして、たくさんの気づきが、年齢を問わず、新たな道を切り開いていくことができるのだと思います。
「スキーマ」という考え方を用いて、生きづらさの正体をつかみ、希望のある未来を築いていけたら…と思う方は活用してみてください。