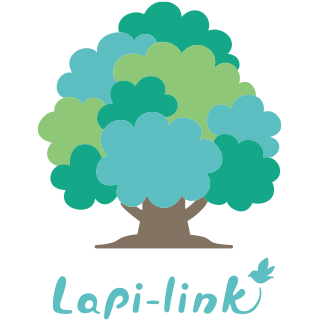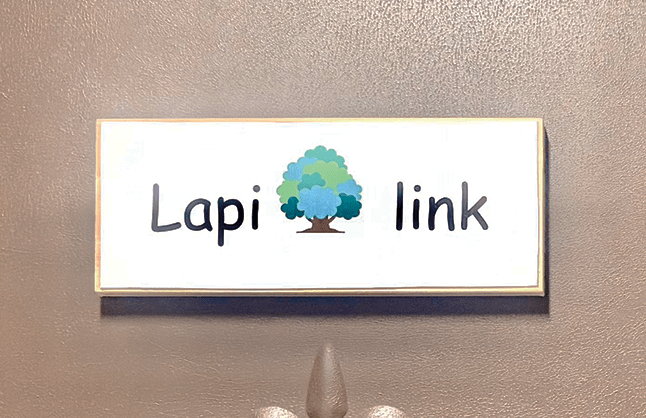愛着形成の重要性は、いくら言っても言い過ぎることはありません。なのに何故、人は愛着を軽視してしまうのでしょう。いや、軽視しているつもりはないのかもしれません。むしろ、それ以上に気を取られてしまうことがたくさんあるのかもしれない。例えば、目につく子どもの言動だったり、冷ややかな周囲の目だったり、ちゃんとした子どもに育てなくちゃいけないというプレッシャーだったり。心の余裕を失えば、子どもの心を感じることができなくなります。
心の余裕とは、努力してつくるものではありません。安心に包まれた中で、自然に生まれてくるものです。ということは、大人の安心が脅かされているということになります。大人の安心が奪われれば、子どもに安心を提供することはできません。それが常態化すれば、生涯子どもを守ってくれるはずの愛着にヒビを入れてしまうかもしれないのです。少子化の問題の根元はここにあります。
そんな思いから、今回は、なぜ人は愛着を軽く捉えてしまうのか、その理由を考えてみました。
愛着が軽視されてしまう理由
愛着形成とは幼少期に重要なもので、大人にとってはあまり関係がないと思っている人は少なからずいるように思います。そもそも愛着が何なのかよくわからない。愛着の概念は納得できるし、その大切さもわかる。わかるけど、その大切さを『ああ、これか』と実感することができない。万が一、愛着形成がうまくいかずに不安定なものになってしまったら、取り返しがつかないものなの?…などなど、いろんな疑問が湧いてきます。そこで今回は、愛着の本質について少し触れてみたいと思います。
愛着って?
一般的に愛着とは、簡単にいうと「子どもが特定の人に抱く情愛のきずな」といわれます。これはイギリスの精神科医ボウルビーが提唱したもの。彼は、生まれてから数年間(2〜3年)が特に重要だといいました。何故なら、子どもが体験する初めての人間関係である親との関係(主に母親)が、後の対人関係に強く影響するからだといったのです。
確かに、なんとなくそんな気もしますよね。なので、ここで異論を述べる人は少ないんだと思います。ところが、重要性は?となると「よくわからない」というのが本音なんだと思います。まず、誕生後の親との関係について、もう少し詳しくみていきますね。
お互いに惹かれ合うように仕掛ける
赤ちゃんに母乳を与えるのは母親になります。実際に子どもを産んだ女性の体内ではホルモンが大きく変動し、その影響で我が子に没頭し、子どもに対して強い愛着を持つように仕向けられます。それは、これから長い人生を生きていく子どもにとって、安定した愛着が何よりも重要だということを意味します。
子ども側にも興味深い仕組みがたくさん備わって生まれてきます。例えば、抱いてもらいながら口いっぱいにおっぱいをふくんで、見つめる先はお母さんの顔です。子どもの視力は、ちょうど20cm先に焦点が合うようにして生まれてくるので(20cm先には抱いてくれる人の目があり、この黒い二つの点を見つめるようになっているんです)自然とお互いに見つめ合うように仕組まれているんです。
お互いに惹き合う中で形成されるのが<愛着>です。子どもからすれば、「安心する」「大切にされている」「自分は歓迎されている」といった、漠然とした感覚が芽生えます。やがてその感覚は、特定の人を識別するようになり、特別で大切な人と「いつも心を通い合わせたい」「見つめ合う心地よさをもっと感じたい」「関心ごとを共有したい」と思うようになります。この過程は、やがて親が提示する「しつけ」に対しても、功を奏するようになるのです。
しつけはある意味、子どもを不快にさせる行為です。やりたい放題はダメだと制限をかけ、時には「こうしなさい」と強要する行為でもあるからです。ただ、大事なのは、しつけが必要な段階に入る前に、しっかりとした愛着を作っておかなくちゃいけないし、しつけをしつつも、同時に愛着形成を続けなければいけないのです。そのことが感覚的にわかるからこそ、母親は苦しくなるのです。
しつけは心の発達に合わせてやるもの
しつけの難しさは、子どもを育てたことのある人ならわかります。場所をわきまえず走り回る。人のものを奪い取る。
思う通りにいかないと泣き叫ぶ…。いくら言ってもわかってくれない苛立たしさと不甲斐なさに、大の大人も泣きたくなるような気分に襲われるほど、しつけは難しいのです。厳しく制して泣き出せば、叱り過ぎたと罪悪感に襲われるし、後々まで「これでよかったのか」「愛情不足で心が荒んでいかないか」と心がうずくのです。
多くの場合、親も試行錯誤をくり返しながら、いい塩梅のほどよさを感覚でつかみ、反省したり、自信を持って立ちはだかったりしながら、しつけに必要なスキルを高めていくのです。
大事なのは二つ。抱きしめることと、立ちはだかること。この二つは、どちらかに偏りすぎてはいけません。そしてもう一つ。成長に合わせて、子どもの世界を全て知ろうとはせず、見えない世界を作っていく。他人や社会にお任せしていく、つまり、ちょっとずつ離れる<子別れ>も重要になります。子どもは、親以外の人(大人や子ども、子どもを取り巻く社会)の中で、時に不快な体験をしつつ、受容されたり、褒められたりしながら、社会性を身につけていくのです。
この当たり前だった成長の過程が、今、とても難しくなっているようです。世の中は、他人に対して無関心だし、親の役割や責任を一緒に背負おうとしてくれる人はいないので、いつも気を張って、ピリピリしながら育てなくちゃいけないからです。
大人自身の愛着のカタチ
さらには、親自身の愛着のカタチも、以前より増して影響力を持つようになりました。当然のことですが、全員が安定した愛着を有しているわけじゃありません。昔のように、親以外にも子どもの心に触れる大人がたくさんいてくれた時代は、親がどうであれ、さほど問題にもならなかったのですが、他人の介入が乏しくなった現代は、親自身の不安定な愛着は、中和されることなくダイレクトに子どもに影響を与えます。しかも長期に渡り。
不安定な愛着を抱えていれば、人一倍不安に襲われるし、不安は心の痛みを引き出しやすくなるので、イライラして怒りっぽくなるし、それがあまりにも苦しければ、無関心になって感じないようにすることで、なんとか対処するようになります。つまり愛着とは、困難に遭遇した時、脅威が迫ってきた時こそ、その力を発揮しますので、安定・不安定が如実にあらわになるのです。
安定した愛着を持つ大人であれば、困難な状況になっても、人を信じて、上手いこと人に助けを求めることができるし、危険であれば安全なところに逃げることもできる。何よりも「なんとかなる!」と自分を信頼して挑もうとします。
つまり愛着とは、子どもだけでなく、大人こそ大切に扱われるべきものなのです。そして、自分の愛着のカタチに関心を向けて、メンテナンスに心を配る必要があるのです。そのためには、愛着とは何か、どうやって補強すればいいのかをしっかりと学んでいく必要があると思うのです。