人格の5因子モデル(ビッグファイブ)に基づいて開発されたNEO-PI-Rという心理検査があります。これは、人格を細かい特徴まで捉え、尚且つ、包括的に理解するために、5つの次元を細かく細分化させています。
今回は、5因子(「N 神経症傾向」「E 外向性」「O 開放性」「A 協調性」「C 誠実性」)のうち、「E 外向性」についてまとめてみたいと思いますので、自己理解を深めるにあたり、参考にしてみてください。
外向性の包括的理解
外向性とは、社交性や積極性の高さを示します。この値が高ければ、新しい経験を好み、人との交流も活発で、エネルギッシュな傾向を持ちます。反対に低ければ、一人の時間を大切にし、どちらかというと内向的で、静かな環境を好む傾向があります。NEO-PI-R人格検査では、さらに細かく6つの下位次元に分けられるので、ご自分の特徴をより深くつかみやすくなります。では、下位次元をみていきましょう。
外向性の6つの下位次元
下位次元1 温かさ
温かさとは、他者に対する親しみやすさや思いやり、優しさを示すもので、他者との密接で感情的な心の絆を意味します。この値が高いと、人の気持ちに敏感に対応し、共感性が高く、相手の立場に立って考えることができます。反対に低ければ、他者と距離を保ち、感情表現は控えめで、客観的で論理的な関係を築く傾向があります。悪気はなく、自分の考えや意見を優先することが多くなるかもしれません。
下位次元2 群居性
人との付き合いを好むかどうかを示すもので、温かさが人間関係の質を示すならば、群居性は、他者との交流や集団活動など、社会的刺激の量を指します。この値が高いと、陽気でエネルギッシュで、人と出会い、仲間になっていくことを楽しむ傾向があります。反対に低ければ、なるべく社会的な刺激を避けて、一人でいることを好む傾向があります。
下位次元3 主導性/断行性
自分の考えや意見をためらわずに言い、積極的にリーダーシップを取っていくかどうかを示します。この値が高いと、目標達成のために方向性を示したり、他者を動機づける役割をとることが得意で、社会的にも優位な立場に就くことが多くなります。反対に低ければ、目立たないことを好み、どちらかというと他人が話すのを聞いている側に立つことが多くなります。
下位次元4 活動レベル
活動のテンポの速さや、精力的な行動を取りやすいかを示します。この値が高ければ、エネルギッシュで多忙な生活を好む傾向が高くなります。この値が高い人は、常に忙しそうにしていて、生活のペースが早いのが特徴的です。反対に低ければ、テンポはゆっくりで、ゆったりとしていて、落ち着いた印象を持たれます。
下位次元5 刺激希求
刺激的なものを好む傾向が高いかを示します。この値が高ければ、刺激的なものや経験を切望し、新しい活動やリスクを伴う経験に対しても、ワクワクしながら積極的に取り組もうとします。変化や多様性を好む傾向もあり、冒険心と関連が高いといわれます。反対に低ければ、高値の人が退屈しそうな、ほんの少しの刺激でも、満足する傾向があります。変化よりも安定性を好み、なるべくリスクは避けて、予測可能な環境を好みます。
下位次元6 肯定的感情
ポジティブな肯定的感情(幸せ、喜び、愛情など)を経験する傾向を示します。この値が高ければ、楽観的で、明るく陽気で、笑顔が多く、よく笑い、人生に満足している傾向を持ちます。反対に低ければ、必ずしも不幸というわけではありませんが、溢れんばかりの、はつらつとした元気さは乏しくなります。
これらの下位次元をまとめて総括的にみた場合、一般的外向性の高い人・低い人はどのような特徴を示すのか「感情面」「行動面」「対人関係」「職務適性」にわけて、みてみますね。
外向性の高い人・低い人の特徴
外向性の高い人
<感情面>
楽観的で、ポジティブな感情を持ちやすい。
<行動面>
エネルギッシュで、いろんな活動やイベントに積極的に参加する。
<対人関係>
他者との交流を積極的に行い、新しい出会いやみんなと一緒の活動を好む。
<職務適性>
人と関わる機会の多い職業(接客・営業・教育など)に適性が高い。
外向性の低い人
<感情面>
慎重で、物事を深く考えることを好む。
<行動面>
控えめで、少ない人数の集まりや個別での交流を好む。
<対人関係>
一人の時間を大切にする。静かな環境を好む。
<職務適性>
高い集中力や思考力を必要とする職種(研究・技術・クリエイティブなど)に適性が高い。
いかがだったでしょう。
この傾向の高い・低いは、決してマイナスではありません。むしろ特性を生かし、適材適所を選ぶことで、チームの活性化や多様なアプローチを開発することができます。外向性が高値であれば、多くの人を巻き込みながら新しい企画を推進していくことを楽しむでしょうし、外向性が低値であったとしても、チーム活動の中であれば、深い分析や計画立案で貢献したり、深い思考力から生み出される研ぎ澄まされたアイデアなどは、周囲を驚かせることもあります。
外向性という特性の理解を深めることで、自己理解、他者理解を深めていただければと思います。
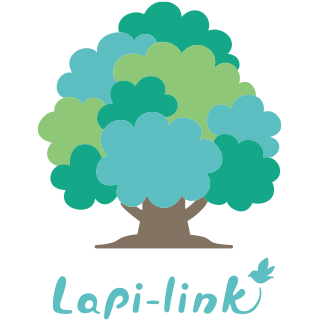












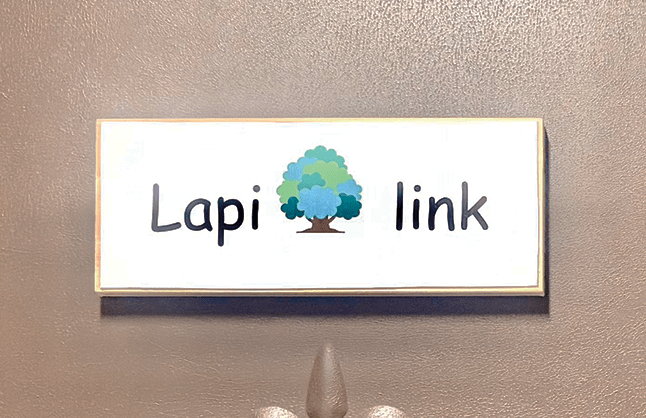
コメント