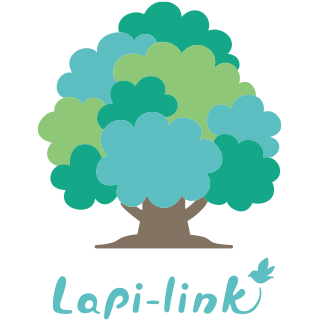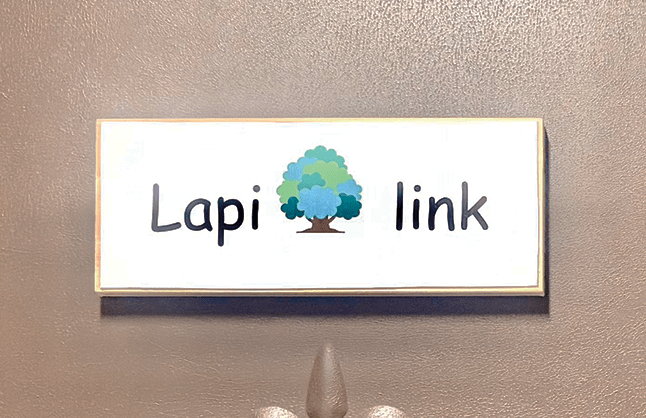性格は生まれ持ったものだから変えようがないと考えがちですが、本当にそうでしょうか?
確かに「この性格、本当に変わらないよなあ」と思う人がいるかと思えば、別人のように変化する人もいます。
性格は変わるのか。それとも、変わらないものなのか。性格形成について考えてみたいと思います。
不安に揺れる親の気持ち
子どもは3歳を過ぎる頃から「お友だちの輪に入れずポツンとしている」「すぐにカンシャクを起こすので、周りから”乱暴な子”と見られてつらい」といったお悩みが増えてきます。どれも違うように見えるのですが、共通点も見えてきます。それは「個性を摘むことなく育ててあげたいけれど、個性が強すぎても輪から外れてしまわないかと将来が心配」という声です。きっと多くの方が、この二つの間で揺れながら子育てを頑張っているのだろうと思います。
マイナスは要らないから、プラスだけ頂戴⁈
ただ、よく考えてみると、ちょっと不自然な点も見えてきます。つまり、パッと見、必要なものだけ残して、不要なものは消して欲しいとか、「無い」ものを「在る」ようにして欲しいといった思いを感じてしまうのです。世の中的に見てプラスなものは磨いてあげるけど、マイナスは要らないので無くしましょうというのはおかしな話です。そもそも大人の役割とは、子どものあるがままを受け入れ、時間をかけて、マイナスに見えるものをプラスに変えていくことです。
怖がりであれば、繊細さとして磨きをかける。
落ち着きのなさは、行動力にシフトさせる。
こだわりの強さは、粘り強さとして生かす。
気づけばどれもかつては不用だったもの。でもそれが、いつの間にか魅力が引き出される。短所だと思っていたものが長所にすり替えていくのが大人の仕事だと思うのです。
遺伝情報スイッチのON/OFFを決める「エピジェネティクス」
ここで、ちょっと興味深い実験をご紹介しましょう。ミツバチの実験です。
ミツバチは、見事な連携プレーを発揮する、社会性の高い昆虫で知られています。まず、ミツバチの中から、おとなしい性質のミツバチと、どう猛な性質のミツバチを選び出します。そして、各々の幼虫を、孵化1日目で入れ替えたのです。すると、おとなしい性質のミツバチが攻撃性を発揮し、どう猛な性質のミツバチがおとなしい性質へと入れ替わったのです。これには驚きました。そこで原因を調べていくと、どうも置かれた環境によって、遺伝子をONにしたり、OFFにする仕組みがあることがわかりました。これを「エピジェネティクス」といいます。
詳しくみていくと、どう猛なミツバチは、他のミツバチよりも、警戒心を働かせるホルモン(警戒ホルモン)を活発にさせる遺伝子をOFFにし、おとなしいミツバチは、警戒ホルモンが活発になる遺伝子をONにして、攻撃性を発揮するようになっていたことがわかったのです。つまり、親から受け継いだ遺伝情報のスイッチが、育つ環境刺激によって、ONになったりOFFになっていたのです。このことによって、何が人をつくるのかという問いに「遺伝じゃない?」「いや、環境でしょ?」と、長い間論争があったのですが、ひとまずの決着がついたのです。
氏か育ちかではなく、その間を埋めるもの
人間で例えるならば、一卵性双生児の研究が有名ですね。遺伝情報が全く同じなのに、好き嫌いや性格、からだの特徴など、様々な点で違いが見られるのは、エピジェネティクスの影響によるものだったのです。つまり、遺伝か環境かのどちらでなく、ちゃんとその間を埋めるものが用意されていたというわけです。このことを、子どもの性格形成に置き換えてみると、同じことが言えるのかもしれません。
おとなしい子・やんちゃな子・マイペースな子、子どもの個性はいろいろ。危険なことが大好きな子もいれば、怖がりで引っ込み思案な子もいるし、細かいことは気にしない大雑把な子だっています。
本当は、人間の持って生まれたものに、無駄な性質なんて一つもないんです。どの性質も、生きるためには欠かせない大切なもので、そこに優劣や価値の高低差をつけるのは、大人たちが営む社会の物差しになるのです。
個性を価値あるものに仕上げるのは大人の仕事
どんな遺伝的な要素を持って生まれてきても、「世の中は恐ろしいところだぞ」と言って聞かせれば、警戒心の強い大人に成長するし、「世の中は可能性に満ちていて素敵なところだ」と言って聞かせれば、行動力のある大人に成長するのです。そばにいる大人がどんな価値観を持ち、どんな判断を下すのかによって、子どもの世界観は変化していくのです。
だとしたら、怖がりな子には「大丈夫、大丈夫」「怖くないから試してごらん」「ほら、大丈夫だったでしょう?」という経験を積ませてあげればいいのです。なんでもやりたがる子には「ちょっと待って、よく見てごらん」と一旦注意を促して、自分が置かれている状況を振り返る習慣を身につけてあげればいいのです。
いかがだったでしょう。性格は生まれ持ったものではなく、つくられるものだということがおわかりいただけたでしょうか?私たちが一般的に呼んでいる「性格」とは、経験→結果の積み上げであり、それはどんな記憶を積み上げたのかということなのです。性格は記憶ですから、本人が望めば上書き保存は可能。過去は変えられなくても、未来の自分をデザインし、実現することができるのです。
間違っても、親が自分の物差しで子どもの将来を計り、最悪を想定しないことです。
きっとこんないいことが起こるね。と、最良の未来をイメージしてあげて欲しいです。