同じ経験をしても、感じ方や受け取り方が人によってずいぶん違うなと思うことがあります。今回は、個人が経験したことをどう処理するのかに焦点をあて、「内在化」「外在化」という概念を解説してみたいと思います。
内在化(Internalization)
内在化とは、外からの刺激を自分の中に取り入れようとすることを指します。わかりやすくいうと、実際に経験したことや、他人の価値観、態度などを自分の一部として取り込みやすくなるのです。例えば、社会的なルールや道徳に忠実であろうとしたり、人から非難されると鵜呑みにしがちで、ひどく落ち込んだりする傾向に現れます。これは子どもが育つ過程でよく見られるもので、私たちの中でもよく起こります。より具体的な例を挙げてみますね。
内在化の例
例えば、以下のようなことがあてはまります。
◉子どもが親の価値観や考え方を自分の中に取り込み、自分の信念として持つようになること。
◉社会のルールや道徳的観念を学習し、それに従って生きようとすること。
◉他人から批判されると、自分を責めるようになること。(例えば、叱責されると「自分はなんてダメな人間なんだ」と思い悩むことなど)
内在化による心の作用
健康的に内在化がすすめば、上手に自分をコントロールできるようになり、自己肯定感や自己効力感などが育まれ、人格形成に影響を与えていきます。ただ、過剰に働き過ぎてしまうと、自己批判が強まり、抑うつ状態や不安、緊張感を高めることになります。
内在化の傾向が強い人の特徴
内在化の傾向の人は、心の活動が活発です。感受性が豊かで、深く内省するし、原因と結果のつながりを理解しようとします。自分が頑張れば、もっと物事をよくできるし、自分の間違いからも素直に学ぼうとします。ただ行き過ぎてしまうと、問題が生じてきます。特に人間関係でダメージを受けやすく、人を不快にさせてしまった時には強い罪悪感に襲われるし、人から厳しく非難されると強い恐怖感に襲われ、不安を抱くようになるようです。それでも、自分が頑張らねばと自己犠牲が行き過ぎた時、一転し「こんなにやっているのに!」と報われない努力に対して強い怒りを覚え、身動きがとれなくなることがあるのです。
外在化(Externalization)
外在化とは、自分の内面で起こる感情や考えを、外部にいる人やモノ、環境のせいにしたり、他人に投影することを指します。失敗やネガティブな感情が起こる原因を、他人や状況のせいにして、自分の心が傷つかないようにする<防衛機制>の一つであるとされています。誰でも多少なりとも当てはまるところはありますが、これが過剰に働くようになれば、周囲との折り合いは悪くなり、結局、生きづらさにつながっていきます。
外在化の例
例えば、以下のような例があげられます。
◉自分の中に湧いてくる怒りの感情を他人のせいにする。(例えば「あの人のせいでイライラさせられているんだ」というように、自分の不快な感情は他人によってもたらされていると捉えます)
◉失敗を環境や他人のせいにします。(例えば「優秀な人材がいないから業績が上がらないんだ」「十分な環境が用意されていないからうまくいかないんだ」「運が悪いんだ」など)
◉内面の不安を他人に向けて、攻撃的になる。(例えば、いじめなど)
外在化の心の作用
外在化が適度な範囲であれば、ストレスの軽減につながっていきます。ところが、過剰に働き過ぎてしまうと、対人関係に軋轢が生じたり、責任逃れの態度が強まってしまい、結果的に生きづらさを抱えることになるのです。
外在化の傾向が強い人の特徴
考える前に行動しがちです(つい相手を不快にさせる言動をとってしまうということも同じです)。それは、不安を早く払拭したくて、すぐさま反応し、衝動的に物事を進めようとするからです。外在化傾向が強い人は、内在化タイプのように内省することはほとんどありません。何かあれば、自分の行動よりも、他の人や環境のせいにします。そして、まわりが変わってくれなければ、自分は幸せになれないという考えに固執しがちですし、自分の望むものを他の人が与えてくれさえすれば、問題は解決すると考えるところがあります。このタイプは、自滅的で破壊的です。極端に自信がないか、自惚れやのどちらかだとも言われています。
人間関係の特徴は、「サポートしてほしい」「安心感させてほしい」という、自分のわがままを受け入れて、甘えさせてくれる存在から切り離されると、強い不安に襲われます。
バランスを崩すと
結局のところ、内在化・外在化のバランスがうまく取れていることが、精神的な健康には重要なのです。
内在化が強すぎると…
「自分はダメだ」「もっと〜しなければ」と自己批判が強くなります。その結果、抑うつや不安を引き起こしやすくなります。
外在化が強過ぎると…
怒りっぽくなり、何かあると他人を責めて、自分の責任を回避するようになります。
つまり、何か問題が生じたり、ストレスが高まった時に、「自分に原因がある」と内在化し過ぎれば、自己嫌悪に陥りやすくなりますし、逆に、「全部まわりのせいだ」「まわりが悪いんだ」と外在化しすぎると、成長の機会を失い、幼い心の状態のまま年齢を重ねることになります。
要はバランスをとることなのです。
結局のところ、いかにバランスを一方に偏らせないようにするか、ということなのです。偏れば、必ず行き詰まる時がやってきます。それでも変えなければ、やがて、うつや不安症、慢性的な緊張や不眠が出現してきます。これらはすべて警告のサイン。今すぐ無理をやめて、本来の自分を取り戻しましょう!と懸命に伝えているのです。もし、そのサインに気づいたら、ぜひ以下のことを行動してみてください。
内在化が強い人は、人に頼ること、助けを求めること、一人で頑張るのをやめる、人間関係のやりすぎをやめること。
外在化が強い人は、自分の心から目を背けない、落ち込むことを怖がらずに「自分が変わらなければ」と思うこと。
極端になるからこそ、問題が生じるのであって、そうでなければ、有益な部分も持ち合わせているということなのです。
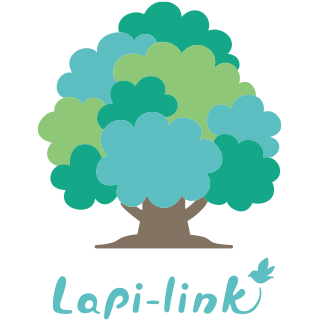

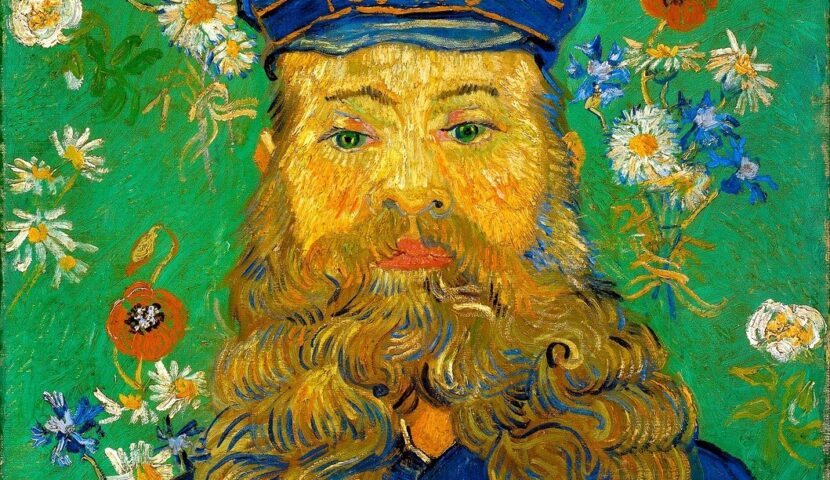
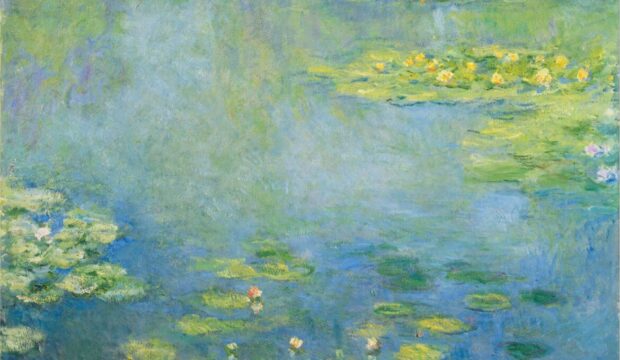









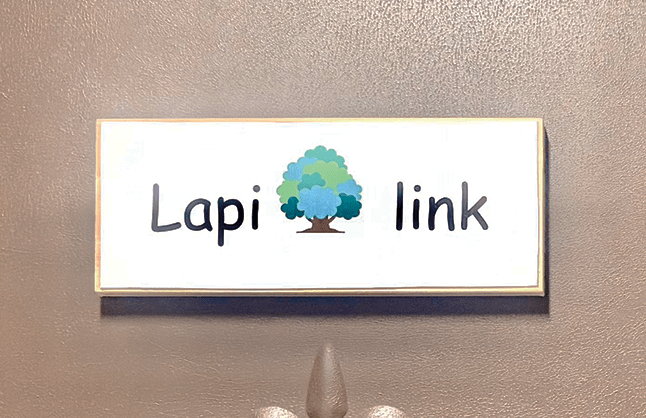
コメント