アサーションとはコミュニケーション方法の一つです。単なる「自己主張」と捉えがちですが、実はとても深い意味があり、相手を尊重しながら自分の意見を伝えることを指します。コミュニケーションがうまくいかない場合、よく見られるのが、一方が自己主張が強く、一方が主張しない関係の場合です。この組み合わせでよく陥りやすいパターンは、自己主張の強い側は、ズバズバと言うことがどんどんエスカレートし、一方は、ますます萎縮してオドオドし自信を失っていく、という固定した関係になることです。こうなると、悪循環は深みにはまっていきます。
その際に、とても力になる方法の一つが、アサーショントレーニングです。アサーションでは、自分の考えを全面に押し出して強く主張することがいいとは捉えません。しかし、かといって完全に受け身になることも賛成しません。どちらか一方の意見を否定して、一方の意見だけを通すのではなく、双方の思いを大切にすることで、コミュニケーションを円滑にしていくことを目的にしています。それでは、アサーションについて概要を少しお話ししていきましょう。
自己主張には4つのタイプがある
まず、自己主張にはいろいろなカタチがあることを理解しましょう。自己主張を観察すると、4つのタイプにわかれるといわれますが、それが以下の通りです。
攻撃的なタイプ
自分の意見を押し通そうとしたり、押し付けることが目立ち、人の意見を聞こうとしません。根底には「自分が一番正しい」という思いがあり、相手をコントール下に置きたいという潜在意識があります。人より優位に立っていたいという気持ちがありますので、人の意見に耳を貸すことは少なく、自分の考えばかりを主張するのが特徴です。自分の意見をはっきりと主張することは、決して悪いことではありませんが、相手を萎縮させたり、周囲と摩擦が生じやすくなり、結果的に、いいコミュニケーションには至りません。偏りが強ければ、自己愛性パーソナリティや境界性パーソナリティの問題も生じてきます。
参照:「自分の思う通りにしたい自己愛性人格」
参照:「つい人を振り回してしまう境界性人格」
受け身なタイプ
攻撃的なタイプの対極にあるのが受け身タイプです。普段からあまり自分の意見は言いません。自分と異なる意見が出ると、途端に自分の意見を押し殺してしまい、相手に合わせるという服従的な態度が目立つ特徴があります。本人は、それが相手を尊重する行為だと思っている節もありますが、本音を言えば、自分に自信がなく、傷つかないように、対立することを回避しているのです。このタイプの多くの人は、傍から見るととても穏やかで優しい印象を持ちますが、人間関係においては、とてもストレスが多くなるタイプでもあります。この偏りがさらに強くなれば、なんでも人に頼る依頼心の強い依存性パーソナリティや共依存の問題も生じてきます。
参照:「受容的で依頼心の強い依存性人格」
作為的なタイプ
作為的なタイプは、一見すると、強い自己主張もなく穏やかで受け身的な印象を持ちます。ところが、裏では別の顔を持ち、とても陰湿な攻撃をするなど、二面性を持ち合わせています。この二面性については、距離が近づかなければ、気づかないことが多いのが特徴で、周囲の人は、何かの拍子に全く想像しなかった裏の姿の事実を知り、びっくりするということも多いです。それは、まるでジキルとハイドが同居しているようにも感じますが、周囲が呆れるような浅くて短絡的なものから、深く巧妙なマニピュレートのような問題が孕むこともあります。
参照:「マニピュレーター心を操る人」
アサーションタイプ
相手の意見に配慮し、その上で、自分の気持ちや考えをしっかりと伝えるのがこのタイプです。アサーションのスキルが最も高い人といえます。たとえ意見が食い違っても、必ずお互いの歩み寄りで、最適な妥協点を見つけようとする、バランス感覚の優れた人です。コミュニケーションの特徴は、自分の気持ちを正直に伝えますが、いいっぱなしではなく、必ず相手の気持ちも確認します。相手を自分の思い通りに動かそうとはしませんし、自分だけでなく、相手も大切にしながら、納得のいく方法を探そうとするコミュニケーションを展開しますので、安心に満ちた心地よい関係を築いていきます。
アサーション・スキルを高める「DESC法」
では、どうすればアサーション・スキルをアップすることができるのでしょうか。最も効果的だと言われているのが「DESC法」です。これは相手とよい関係を築きながら、言いたいこと、伝えたいことをどうやってアサーション的に伝えるかを細かく解説しているものです。最近では、ビジネスの面でも盛んに取り上げられるようになりました。少し説明しましょう。
POINTD:Describe 客観的な事実を述べる
解決したい課題に対して、自分の感情や憶測を入れずに、まず相手の言動や状況における事実のみを伝えます。
E:Explanation 自分の意見や考えを説明する
Dの事実だけを伝えた後、今度は自分の気持ちを素直に表現したり、説明します。また、相手の気持ちに共感することも大切です。とにかく感情や気持ちを、冷静に、明確に述べます。
S:Suggest 具体的な提案をする
次に、課題を解決するためのアイデアや、代替案などを提案します。さらに、相手に望む行動、代替え案、解決策などを提案していきます。
C:Choose 提案の選択
ところが、相手が提案を全て受け入れるとは限りません。提案を受け入れないことも考えられます。その場合は、再度よりよい提案を検討していきます。受け入れる、受け入れない、それぞれに対して、その結果を想像し、どう行動するか選択肢を考えていきます。その上で、積極的な選択肢を示します。脅すことが目的ではないので、相手に断る権利があることを常に念頭に置いていきます。
結論から先に考える
DESC法を用いる場合、最初に相手に伝えたいことから考えるという方法があります。相手にこのことを伝えたい、ということを明確にさせ、そのことを目的に、DESC法を考えるのです。つまり、相手にわかって欲しいことは何かをはっきりさせて、そのためにはDESC法をどう組み立てればいいのかを考えるのです。何を伝えたいのかがはっきりしていなければ、要は何を言いたいのか?と、相手も理解できないでしょう。
人は変えられないことを肝に銘じる
時々、相手を自分の思う通りに動かしたい、という強い欲求を持つ人がいます。長期的にみてみると、必ず人間関係がギクシャクしています。そういう人の特徴は、自分を振り返る力が弱く、同時に、相手の心を汲む力も弱いです。自分のわがままを全て受け入れてくれなければ、強い不満を見せるので、精神的にとても幼く、扱いにくい人です。そういう相手に対して、アサーションスキルは確かに有効です。隷従関係に陥らないようにするためには欠かせないスキルかもしれません。
ですが、決して万能ではなく、あくまでも納得性を高めるための一つの手法だということを心に留めてください。相手を変えることはできないのです。変えられるのは自分だけ。手法に依存し過ぎて、結果的に、相手の心が離れてしまったというケースもたくさんあります。手法に頼り過ぎず、なんのために、この様なコミュニケーションが必要なのか、最終的な目的(どういう関係を築きたいのか、それはなぜか)を明確にして、心を込めて誠実に接することを忘れないことです。(つまり「信頼関係を深めたい、なぜなら仕事でいい成果を出したいからだ」「二人の関係を温かいものにしたい、なぜなら愛情を深めたいからだ」など)
そのためには、どんなことに注意すればいいでしょう。
アサーティブな関係を支える4つの柱
最後に、アサーティブな関係を構築していくために大切にして欲しい4つの柱を説明します。
誠実さ
自分にも、相手にも、素直な気持ちを伝える誠実さを持つことです。たとえ相手と意見が異なった場合でも、相手の意見を受け止めてください。そして、自分の考えをしっかりと伝えましょう。誠意ある態度でコミュニケーションを取ることを心掛けます。
率直さ
自分の気持ちや意見を隠さず、率直に、ストレートに言葉にすることが大切です。曖昧で遠回しな表現をしたり、「誰かがこう言っていた」など、他人を利用すると、相手に本意が伝わりにくくなり誤解の元になります。<Iメッセージ>を意識し、主語は「自分」に置き、「自分は、こう思っている」と正直に主張するようにします。
対等な姿勢
よい関係を築くためには、まず心の中で対等であることです。攻撃的な相手に隷従するような態度では、対等とはいけません。また、言葉を選びながらも、心の中で相手を見下していればそれは相手にも伝わります。特に自分に自信のない人は、知らず知らずに自分を強く大きく見せようとしたり、反対に、過小評価して小さく見せようとする傾向があります。あくまでも対等の関係になっているか、心の中で上下関係が固定化していないかに注意します。
責任
コミュニケーションとは、相手と自分の双方の関係性で成立しています。結果的に相手とのコミュニケーションに不満が残る場合、相手を責めるのではなく、自分の言動に責任を持つことです。自分には発言した責任があり、また、発言しなかった責任があるのです。どちらか一方が「自分は悪くない、問題は相手にある」と考えたり、「自分だけが悪い」と相手の分の責任を背負い過ぎても、対等ないい関係にはなれないのです。
いかがだったでしょう。
興味を持った方は、ぜひDESC法に挑戦してみてくださいね。
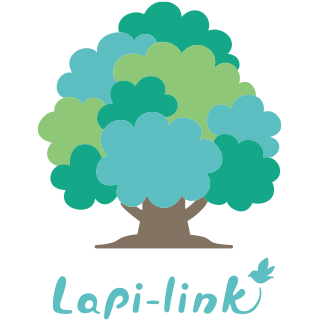

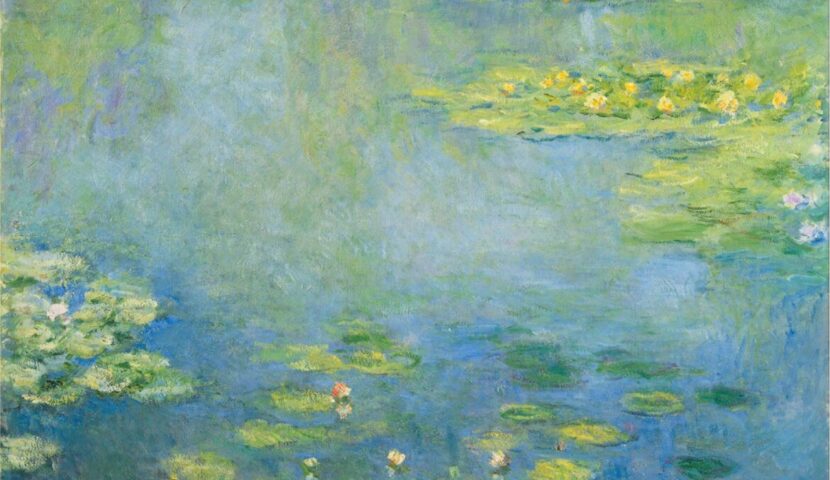










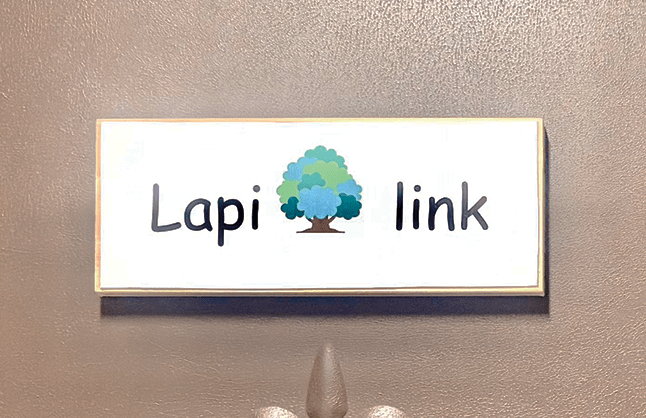
コメント